皆さんこんにちは。早いものでもう3月ですね!
私は新しい環境・生活の中に入るための準備に追われています 😆
さて、今回取り上げるのは、車と言ったら欠かせないタイヤ!
快適な走行や燃費改善のために日々改良されているタイヤですが、
将来はどんな性能・どんな姿へと変わっていくのでしょうか?
一緒にソウゾウしていきましょう 💡
まずは、タイヤがどのような変遷を辿ってきたのか簡単にまとめてみました 😯
(参考:◎タイヤの歴史―TUBELEST、
◎タイヤ五千年の歴史 – 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 JATMA)
タイヤの原型となった車輪はおよそ5千年前に誕生したといわれ、それ以来ほとんどその形状を変えていません。
といっても、当時の材料は木や鉄などで、
特に鉄タイヤの時代はおよそ2千年前のローマ帝国の頃から1900年近くも続いていました!
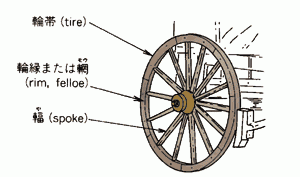
鉄タイヤのつくり(日本自動車タイヤ協会HPより)
タイヤにゴムが使われ始めたのは1867年で、たった130年ほど昔のこと。
そして、現在車などで使用されている空気入りタイヤが生まれたのは1888年、最初は自転車のタイヤに使われていました。
そして、わずか130年ほどの間に
自動車の普及に合わせて空気入りタイヤの幅はだんだん太く変わっていきます。

1880年代からのタイヤ幅の変化(出典:工学院大学、MONOist記事〈リンク〉より)
タイヤの幅が太くなるほど安定感が増し、曲がる・止まるといった操作性能も上げることができるために
このような変化が起きてきたのです。
「じゃあ、このままいけばタイヤはどんどん太くなっていくんじゃない?
ブルドーザーのキャタピラーみたいな形で、もっと高速で走れる仕組みを開発できるかも…」
とソウゾウを膨らませていた私でしたが…
◎元ブリヂストンのタイヤ開発者が語る:未来のタイヤが19世紀のものと同じ形になる理由 – MONOist

今後のタイヤ開発の方向性(出典:工学院大学、MONOis記事〈リンク〉より)
なんと、車のタイヤは将来細く変化し、発明された130年前の姿に近くなるという話が上がっていたのです!
その理由は、環境問題に対する取り組みとして燃費の向上が求められるようになったため。
細いタイヤは、走る際の操作性は通常と比べて不安定になりやすくなる一方、
走る際の抵抗が減り燃費が良くなるというメリットがあるんです。
実際にブリヂストンでは低燃費タイヤ技術「ologic」を開発、
BMWの電気自動車「BMW i3」などで採用されすでに実用化が進んでいます!
記事は2014年11月のものですが、つい最近車のCMを見た際に「心なしかタイヤが細い?」と思ったことがありました(それがBMW i3のCMだったようです)。
タイヤは着実に細くなる傾向に進んでいるようですね!
新たな形に変わっていくだけでなく、
その時代に求められる性能を得るために昔の形へと戻っていく場合もあるというのは
目から鱗が落ちました 😯
💡 ここがソウゾウポイント! 💡
・「未来=全く新しいもの」だけではないことを知ろう。
・重要なのは「何を求められているか?」、ニーズに合わせた姿かたちを模索しよう。
今後のソウゾウは、過去の姿に立ち返ることもきちんと視野に入れなければなりませんね 😉 !
〈第九回ソウゾウ報告〉
◎未来の車への変化は新しくなるものばかりではない! 性能やニーズに合わせ、かつての姿へ戻るのもソウゾウのひとつ。
